このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています
数学ができないって決めつけるのはまだ早いです!
数学が苦手な人って以下のことに当てはまっていることが多いです。
・公式を覚えたのに使えない
・学校のテストは解ける
・模試や実力試験は得点できない
・不登校になって訳が分からなくなった
でも大丈夫、解決できるようになります。
実はこれ、2つの共通点があります。
・「言葉のルール(意味)をちゃんと知ること」が出来てない
・なにを質問(解説)されているのか、考えられてない
国語力とも取られますが、今となっては、分かりにくい言葉はAIが分かりやすく説明してくれます。
例:「〇〇について、小学生でも分かる言葉に置き換えて」
と打ち込めば解決してくれます。
以上の方法をとりつつ、数学で悩んでいることを一緒に考えていきましょう。
さて、この記事を書いた人↓
・個別指導塾で2005年から教室長と講師に従事
・コロナ禍を経て、オンライン家庭教師を副業
室長としては、累計6,000件を超える親子懇談を経験。
さまざまなご家庭(親子関係)を観てきました。
ただ、不登校生対応は僕の力不足もあり難しかったです。
そこで全国にいる不登校生に何かできないかと考え、ブログで発信中。
なぜ数学が苦手になってしまったのか【特徴4つ】
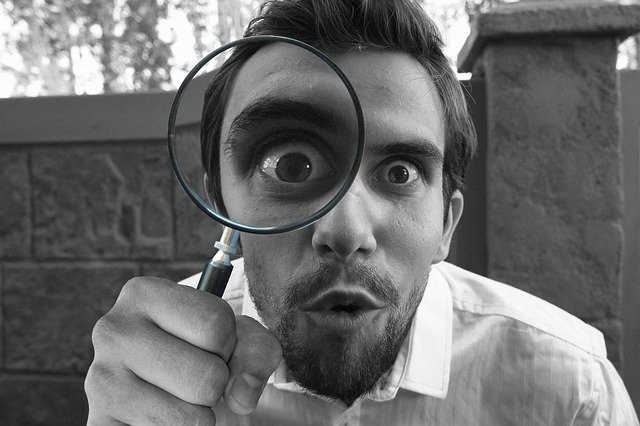
今から伝える4つの事が自分のことだったとしても大丈夫。
あとで述べる手順6つを進めたら数学ができるようになっていきます。
それでは解説していきます。
数学が苦手なのは暗記科目にしてしまっている
数学の公式や解答を、まるで英単語を覚えるような勉強をしていませんか?
暗記したことは良いとして、でも、そんな学習だと無限に覚え続けないといけません。
一度解いたことのある問題や類似問題にしか対応ができません。
せっかく覚えた公式でも、いつ、どこで、どのように使ったら良いのか判断ができないのがオチです。
この勉強は時間を無駄にしてしまっています。
数学が苦手な人:前学年までの基礎が乏しい
あなたが仮に中1生で数学が分からないなら、小学校の算数を理解していない可能性があります。
中1数学は、実は小4の算数から関係していたことを知っていましたか?
数学は積み重ねが大事で、つながり学習とも言われます。
それまでに学習した内容を分からないまま放置し、次の単元に入ってから急に分からなくなることがあります。
前単元終了=理解した前提で進められるからです。
そうなると授業についていけなくなることが出てしまいます。
数学が苦手な人は解答をすぐに見てしまう(問題解決力が養えない)
問題を解いていても「苦手だから」といって、すぐに解答を見ていませんか?
数学の答えはすぐに出ません。
それなのに、「考えるのは苦手」「面倒くさい」という理由で考えることをすぐに諦めてしまっている人を僕はたくさん見てきました。
ここで知ってほしいがあります。
数学を学ぶ最大の利点は、複雑な問題を整理し、筋道を立てて考え、結論を導き出す力(論理的思考)が養われることです。
わからない問題の答えを見ること自体はダメではありませんが、答えを見る前にじっくり考える訓練を積んでほしいのです。
数学が苦手な人は授業を受けているだけ
予習ができれば理想ですが、授業を受けたあとの復習をしないとなると、これでは数学ができるようになるきっかけがなくなります。
授業を「見た、聞いた、解いた」だけで、理解を深めるのは非常に厳しいものです。
自転車に乗れるようになるには、やり方を聴いても乗れません。
教わったことを自分自身で挑戦し続けることです。
学習に言い換えるなら、学んだことを定着するための復習作業が必要だということです。
数学を苦手にしまうと損してしまうこと

非常に生きにくくなります。
何かトラブルを抱えた際、問題解決能力があるかないかで、今後の生き方が変わります。
数学で学ぶものは、計算や文章問題ができるようになるといった表面的な力だけではありません。
計算を抽象的かつ論理的に考えるための思考力を養ってくれます。
それだけではなく、ニュースや経済情報など、現代社会の情報を適切に理解する力が身についていきます。
大人になった時の生活や仕事で数学的なことと関りが薄くなったとしても、「正しく考える力」を磨くことになることを知ってほしいです。
きっと将来にわたって役立つと思います。
数学的な考え方というのは、問題解決能力や判断力を高めることにもなります。
なので僕は、
「数学(算数)は、仕事でのデータ分析、情報(ニュースや統計など)の正確な理解、複数の選択肢から最善のものを判断する際に大いに役立つよ」
と伝え続けています。
数学が苦手な人ができるようになるための手順【6つ】

数学が苦手であれば、あとは「できるようになる」ためのステップが分かれば大丈夫です。
今の実力がどれくらいなのかを知ること
数学は積み重ねが大事です。
自分が理解している範囲を把握し、わからない部分を基礎からしっかり積み重ねていくことで、数学ができるようになっていきます。
実力を知るためには、学校の定期テストや模試の結果を活用するのがオススメです。
試験の結果を見ることで、中学レベルが定着していない、ここまではできている、この分野が苦手というような分析ができます。
とはいえ、数学が苦手な人が、自分だけで自分の実力を分析することは難しいでしょう。
恥ずかしいと思わず、学校や塾の先生に自分の実力がどのくらいなのか知りたいと相談してみましょう。
なお、自分の実力がわかっている場合でも、実力の範囲内(わかっている範囲内)の問題だけを繰り返し解いていては、数学ができるようにはなりませんので、気を付けましょう。
言葉のルール(意味)をちゃんと知ること
数学で出てくるいろんな言葉の定義を覚えることです。
定義とは、その言葉の説明やあらかじめ決められた共通の認識と言い換えることができます。
なぜ定義が大切かと言うと、それが数学の土台だからです。
いろんな言葉の定義をしっかり理解することで、問題の意味や解き方もわかってきます。
例えば、小学校でも中学校でも学ぶ関数について考えてみましょう。
例:比例(関数)
比例・反比例という言葉の意味を理解していないと、この単元はチンプンカンプン状態となります。
比例の問題と分かった瞬間、y=ax が使える発想がすぐに出なければなりません。
そして、この式の中にある「 a 」ですが、中学校では「比例定数」、小学校では「決まった数」だと言えなければなりません。
比例定数=決まった数、であるのは言うまでもありません。
何よりも関数って「どんな意味なのか」が分かっていないと話になりません。
そこで「関数って何?」と調べることで、「2つの量(ここでは、xとy)があり、xが変わるとyも変わる関係のことを関数」といいます。
中でも、比例関係ともなれば、xが2倍・3倍・4倍大きくなると、yも同じように2倍・3倍・4倍大きくなる関係の事を意味します。
上記内容がすぐに出てこなければ、関数の問題は手も足も出ません。
数学を暗記科目にしてしまっていると、比例ってy=ax って言えるけど、でもそれ以上何も説明できないので、問題を解くことは厳しいです。
言葉の意味を理解しておかないといけない理由がここにあるのです。
公式をただ暗記せずに式の意味を知ること
言葉の意味を覚えたのであれば、そこからわかる式の性質も理解できるようになります。
公式が導かれる過程を知るようになると、公式の意味が理解でき、数学を上達し始めるようになっていきます。
実はこれ、数学以外でも、普段の生活でやっていることがあるのです。
意味を理解していると覚えやすいものは、数学以外でもいろいろあります。
例:歴史の年号
学校で学ぶ暗記の代表例となります。
出来事の因果関係や時代の流れをセットで理解すると、単に数字を丸暗記するよりも記憶に残りやすくなります。
たとえば、〇〇の戦争が起こった(原因)→ 〇〇条約が結ばれた(結果)→ 〇〇という新しい制度ができた(影響)。
「なぜその年にその出来事が起こったのか」という背景をストーリーとして理解することが重要です。
数学も同じで、公式がそうなっている理由を理解していると、問題を解く力がグッと上がるのです。
数学の公式を覚えるときも、ただ暗記するのではなく、どういう意味なのか、どう導かれたのかを一緒に覚えておくようにしましょう。
ここで初めて練習問題をたくさん解くこと
暗記ができ、その意味・どう導かれたのか理解できれば、ようやく基本事項の練習問題をこなす段階です。
試験前に多くの課題が学校から出されますが、これまでの手順も踏まずに、いきなり練習問題を解く人が得点できないのは、ここから始めているからです。
正しい手順を踏んだうえで、たくさん解けば解くほど、数学はできるようになります。
どれを選べばいいのかわからないかもしれませんが、まずは学校教材を徹底的に繰り返しましょう。
あえてほかの教材を選ぶなら、例題がたくさん載っていて、解説が多いものをおススメします。
まずは公式の理解と専門用語の理解。
これらができていないか、これまで勉強したはずの単元の内容を再チェックしてみてください。
応用問題にチャレンジすること
基礎的な問題が解けるようになったら、応用問題にチャレンジです。
ここで大事なのは、解ける・解けないではありません。
応用問題に触れ、考える行動をとることが重要となります。
でもどれが応用問題なのかわからない?
例えば、以下のような感じです。
- 入試レベルと書いてある
- 発展問題のページ
- 重要例題と書いている
- 実際の入試の過去問
(学校名が書かれているもの)
応用問題は公式を当てはめるだけで終わるものではありません。
公式が少し変化していたり、組み合わせてとくような過程が求められます。
段階を踏んで解くイメージです。
考えていかなければなりませんが、考え続けることに挑戦してみてください。
「わからない」のは当然ですが、すぐにあきらめると、数学ができるようにはなりません。
数学的思考力を積むには「考える作業」が必要です。
1問につき5分以上考えるところまで続けてください。
最後に問題の答えを見よること
ここで初めて答えを見る作業に入ります。
数学が苦手な人は、ここを最初にしてしまっています。
ただ、これまで述べてきた流れで、5分以上考えてもわからないときは、思い切って答えを見ていってください。
ただし、以下のことを強く意識してほしいです。
- 問題文の中で大事な情報は何か?
- 使われている公式がなぜ必要だった?
- 自分に足りない知識は何だった?
この3つを考えつつ、答えを見て、自分の言葉で説明できるようにすることが重要。
せっかく覚えた公式をいつ・どこで・どのように使うかを判断する力を鍛えてほしいです。
数学力は簡単には身に付きません。
でも3つの行動がついてくれば、応用問題であっても、少しずつ少しずつ簡単に解けるようになっていきます。
なので今わからなくても大丈夫。
落ち込む必要もないです。始まったばかりですから。
あなたに伝えた6つのステップを一歩一歩進めていけば良いです。
時間差で理解できるようになります。
ポイントは、わからなくても5分続けてください。
考える作業を大事にしましょう。
数学が苦手:続ければ克服できるようになっていきます

今回は数学が苦手な人に向けて書きました。
でもこれって、どの勉強でも通ずるものだと思いませんでしたか?
大事なことは2つ。
- 正しい手順で勉強
- まず考え続ける
その場で答えが出なかったとしても問題なし。
上記2点を続けることです。
今後生きていく「問題解決能力」までも身についていくようになります。
それでも1人できないのであれば、何かに、人に頼ってみてください。
自分に合った家庭教師の見つけ方↓

不登校生も頑張れる通信教育↓

今回のおさらいです。
数学ができない人の特徴
- 数学を暗記科目にしてないか
- 問題の答えをすぐに見てないか
- 前学年の基礎を放置してないか
- 予習・復習を続けているか
数学ができるようになるには、次の手順を守る。
- 自分の実力を知る
- 言葉の理解に努める
- 公式をただ暗記せずに式の意味を知ること
- 練習問題をたくさん解くこと
- 応用問題にチャレンジすること
- 最後に問題の答えを見よること
どうか数学の成績に変化が出て来るまで続けてください。
応援しています!それでは!


